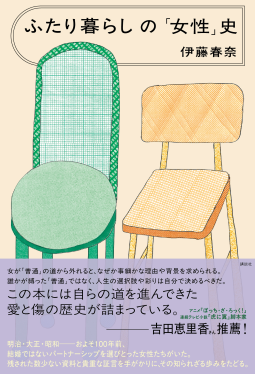
ふたり暮らしの「女性」史
伊藤春奈
この作品は、現在アーカイブされています。
ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。
出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。
1
KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。
2
Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。
刊行日 2025/03/25 | 掲載終了日 2025/03/18
ハッシュタグ:#ふたり暮らしの女性史 #NetGalleyJP
内容紹介
連続テレビ小説『虎に翼』アニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』
~~ 脚本家・吉田恵里香さん推薦!~~
明治・大正・昭和――
およそ100年前、結婚ではないパートナーシップを選びとった女性たちがいた。
残された数少ない資料と貴重な証言を手がかりに、その知られざる歩みをたどる。
~・~・~・~・~・~・~・~
「女性」を歴史に残すこと、
歴史のなかの生活が軽視されがちなこの社会で、
ふたり暮らしを実践した人たちの、消えそうな足跡をたどってみたい。
―― 序章 ふたりだけの部屋で生きる より
~・~・~・~・~・~・~・~
【目次】
序章 ふたりだけの部屋で生きる
第1章 語られなかったふたり暮らし――人見絹枝と藤村蝶
第2章 帝国日本とふたり暮らし――飛行士たち
第3章 主従関係とふたり暮らし――五代藍子と徳本うめ
第4章 語り継がれるふたり暮らし――斎藤すみと芳江
----------------------------
著者/伊藤春奈(いとう・はるな)
1978年生まれ。編集者・ライター。2020年より女性史を中心とした出版プロジェクト「花束書房」を主宰し、『ウィメン・ウォリアーズ はじめて読む女戦記』(パメラ・トーラー著、西川知佐訳)、『未来からきたフェミニスト 北村兼子と山川菊栄』、『帝国主義と闘った14人の朝鮮フェミニスト 独立運動を描きなおす』(尹錫男絵、金伊京著、宋連玉・金美恵訳)を刊行。フェミニズムマガジン『エトセトラ』VOL.9特集「NO MORE 女人禁制!」を編集。著書に『「姐御」の文化史 幕末から近代まで教科書が教えない女性史』(DU BOOKS)などがある。
出版社からの備考・コメント
発売前の大切なゲラをご提供させていただいております。弊社では、下記のような方からのリクエストをお待ちしております。
○発売に向けて、一緒に作品と著者を応援していただける方
○NetGalleyへレビューを書いてくださる方
○自分には合わない内容だった際、どういったところが合わなかったかなど、建設的なご意見をくださる方
下記に該当する方のリクエストはお断りさせていただく場合がございます。
ご理解のほど、宜しくお願いいたします。
○お名前・所属などに詳細な記載がなく、プロフィールにてお人柄が伺えない方
○作品ごとに設けました外部サイトへのレビューのルールをお守りいただけない方
○フィードバック率の低い状態が長く続く方
-----------------
※※リクエストの承認につきましては現在お時間をいただいております。
おすすめコメント
~・~・~・~
明治・大正・昭和――
この時代に、結婚や家族ではないパートナーシップを選びとり、「女性どうしのふたり暮らし」をしていた人々がいた――。
日本人女性初のオリンピックメダリストである人見絹枝や五代友厚の娘・五代藍子など、「こう生きよ」とあらかじめ方向づけられた生き方ではない暮らしを選んだ女性たちの歩みを辿ることができる一冊です。
~・~・~・~
~・~・~・~
明治・大正・昭和――
この時代に、結婚や家族ではないパートナーシップを選びとり、「女性どうしのふたり暮らし」をしていた人々がいた――。
日本人女性初のオリンピックメダリストである人見絹枝や五代友厚の娘・五代藍子など、「こう生きよ」とあらかじめ方向づけられた生き方ではない暮らしを選んだ女性たちの歩みを辿ることができる一冊です。
~・~・~・~
販促プラン
★
読み終わりましたら是非NetGalleyへレビューをご投稿ください!
著者・担当編集者ともに楽しみにお待ちしております。
また、適したメディアやお持ちのSNSにもレビューを投稿いただき、多くの方に本を拡げていただけますと嬉しく幸いです。
※発売前作品のため、ネタバレになるレビューはくれぐれもお控えくださいませ※
ご協力の程、何卒宜しくお願いいたします。
★★★
作品の拡材や指定配本をご希望の書店様は
恐れ入りますが<講談社 書籍営業部>まで直接お問合せをお願いいたします。
★★
出版情報
| ISBN | 9784065388679 |
| 本体価格 | ¥1,800 (JPY) |
| ページ数 | 256 |
関連リンク
閲覧オプション
NetGalley会員レビュー
 レビュアー 781279
レビュアー 781279
あなたの隣の家で女性がふたりで暮らしていたら、そのふたりはどんな関係だとあなたは考えますか?家族でしょうか?友人でしょうか?恋人だと考えますか?
明治から大正、昭和という時代を経て約100年。
女性たちは社会から軽視されながらも、パートナーとして共に暮らすことを選びます。
歴史に名前を残す女性たちに、口さがない人たちは二人の関係を噂します。
特に第一章・人見絹枝と藤村蝶の章では、人見絹枝の残した言葉を読むにつれ涙がこぼれました。アスリートとして、新聞記者として多忙な日々を送りながら、自分の言葉を綴る人見絹衣。歴史に名前を残すメダリストとしてとしか知らなかったのでこんな思いをしていたのかと初めて知りました。
人見絹枝と藤村蝶の関係を詳しく知りたいとは思いません。ただ二人が同じ墓に埋葬されていることを知ることが知ることが出来ただけで十分です。
女性がふたりで暮らしていたら、その関係に名前を付けることが必要でしょうか?
そんな必要はないのです。ただふたりは一緒に暮らすことを選んだだけなのです。
ふたりにしか分からない関係性と絆がそこにはあります。
家制度に縛られず自分の信念で生き、女性のふたり暮らしを選んだ先人たち。
そのふたりの背景や、関係性は様々ですが彼女たちの足跡を辿ることで今に通じるレールが敷かれたことを知りました。
しかし100年経っても同性で暮らしている人への興味本位の噂が絶えないことが残念でなりません。
ふたり暮らしを選んだ女性たちを通して、今私達は何を問われているのでしょう。
そんなことを考えながらぜひ読んでほしいです。
 レビュアー 530109
レビュアー 530109
女であるだけで差別される。まずは業界へ入る段階で「女人禁制」だと言われる。何故だと聞けば「穢れる」「風紀が乱れる」「女には無理だ」と言われる。わずかなスキマを見つけてその世界へ入り、必死に頑張る女性たちは、髪を短くし、胸が目立たないようにさらしを巻き、男性の服装をする。すると「男装の麗人か」と揶揄される。
「虎と翼」のヨネさんと同じ、そこまでしなければ生き残れない世界です。そんな無理して仕事なんかしてないで、普通の女に戻って嫁に行けという同調圧力は余りにも強かったのです。そして、100年後の今も、ちっとも変ってない。
この本に登場する「ふたり暮らし」する女性たちは、きっと「同士」という絆で生きていたのだと感じました。だって、どうしようもない差別と闘うのに、ひとりでは辛過ぎます。同じ思いを持つ人がそばにいてくれるから、耐える力が湧いてきたのではないでしょうか。
今は、昔よりもマシにはなったけど、女性の権利ということを考えると、まだまだなことばかりです。家事労働は軽んじられたままだし、家制度の呪縛から逃れるために都会へ行く女性は増えるし。選択的夫婦別姓だって、いつまで待たされるのか分からないし。百年経っても基本的なところは変わらないのだなと、ため息ばかりが出てしまうのです。
 レビュアー 1044791
レビュアー 1044791
嫁に行くことがスタンダードの時代に「女性」の二人暮らしを選んだ人びとにフォーカスを当てた本書、ありそうでなかった切り口でたいへん興味深く拝読しました。そうした人びとへの当時の言説や報道はちょっと時代を感じるものが多かったです。個人的な話になりますが、自分自身のまわりにも、女性どうしでルームシェアしている話は珍しくないものになっていて、それが可能になっているのはきっと本書に登場したような人びとの有形無形の訴えや活動の積み重ねがあったからなのだろうと思います。
 レビュアー 1114213
レビュアー 1114213
近代化というブルドーザーが押し込めようとした家父長制度という鋳型にはまらず「自分で決めた」女性たちの物語。
陸上選手、パイロット、鉱山師、騎手。
ただ自由に、愛しいと思う相手と暮らしたかっただけの彼女たちの足跡をたどる。
「人が、ただの個人として生きることはなぜこんなにも難しいのだろう」
 書店関係者 1084454
書店関係者 1084454
ここに書かれた女性たちは、たとえば子ども向けの伝記シリーズでとりあげられるような有名人ではない。実際私もよく知らなかったり、名前を初めて聞く方も多かった。だけれど、最後の章にあるように、今不十分であっても、昔にくらべて私たち女性が声を上げやすくなってきているのは、彼女たちが今よりずっと理解されない状況のなかでも、自分であることを諦めずに生きようとしてきたからだ。そのような歴史の上に立たせてもらっている、生きさせてもらっていることを忘れてはいけないし、私たち自身も男性も女性も誰もが生きやすい世界に未来がなるよう声を上げ続けていかなねばならないと感じた。
 教育関係者 468529
教育関係者 468529
女性同士で生活する、または結婚をしないという選択。
この選択は現代ではどのように見られるのか。
今でもある一定の年齢より上の世代は、軽々しく「結婚しないの?」「良い人はいないの?」と
孫や若い世代の人たちに聞く。
何の悪気もなく。家父長制の残滓はまだ濃く人々の意識に沈んでいることがわかる。
ましてやこの本に書かれている時代ならどうだろうか。
「気にしないで自分の生きたいように生きる」ことに非常に勇気と自分の芯を持たねば暮らしていけなかったのでは
ないか。
この本によって示唆されている「男装の麗人」という言葉がすべての理解のカギの一つだ。
どのような背景があるかも想像すらせず、男装の麗人という言葉で一括りにして表現することで
自分たちの理解が及ばないことをひた隠しにし、自分たちの枠のなかでそれを理解した気になって押し付ける。
ここから気づいたことは言語化というのがいかに大切なことかということだ。
「ハラスメント」という言葉が膾炙しているし、使われているが、この言葉がなかったころは
どうしていただろうか。またどうしてハラスメントが日本語に変換されていないのだろうか。
この本を読んでいて、思考も広がりまた周りに勧めて感想を聞きたいと思った。
 図書館関係者 601014
図書館関係者 601014
知らない方が多く、でも知られることがなかったことにも意味があると思いながら読みました。
ふたり暮らしの「女性」も生きづらかったことはひしひしと伝わってきましたが、
それは「女性」というジェンダーの経済的な自立の難しさによるところも大きく感じられ、
その場合「男性」のふたり暮らしというのはどうだったのだろうと気になりました。
経済的には問題なくても、当時の価値観的には女性同士と男性同士とどちらがより目が厳しかったのか。
でも、そんなことより、一緒に生きたい人(がいない人は一人で)と自由に生きられる世の中であってほしいと、
しみじみと考えさせられました。





