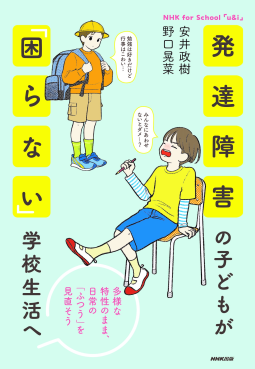
発達障害の子どもが「困らない」学校生活へ
多様な特性のまま、日常の「ふつう」を見直そう
安井政樹/野口晃菜
この作品は、現在アーカイブされています。
ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。
出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。
1
KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。
2
Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。
刊行日 2025/02/25 | 掲載終了日 2025/02/24
ハッシュタグ:#発達障害の子どもが困らない学校生活へ多様な特性のまま日常のふつうを見直そう #NetGalleyJP
内容紹介
「“ふつう”じゃないに気づくこと。それは同時に、可能性に気づくことだと思う。」――松田崇弥さん(ヘラルボニー代表取締役)推薦!
授業中座り続けるのが苦手な子、イベントが苦手な子、周りにあわせた行動が苦手な子など多様な子どもたちがいる学校の「ふつう」の数々。発達障害の子どもをはじめさまざまな子どもたちのバリアになっている身の回りの「ふつう」をアップデートし、バリアを取り除くためのアイデアや実践のヒントを、学校現場での経験や知見が豊富な著者たちが事例満載に紹介。マンガなどでわかりやすく伝える、保護者や先生にお勧めの実践的な1冊!
巻末に伊野尾慧さん&きゃりーぱみゅぱみゅさんと「ふつう」について考えて語り合った特別座談会を収載。
販促プラン
事前注文書作成
出版情報
| 発行形態 | ソフトカバー |
| ISBN | 9784140819845 |
| 本体価格 | ¥1,650 (JPY) |
閲覧オプション
NetGalley会員レビュー
 レビュアー 946550
レビュアー 946550
そうかあ、NHK for school のエッセンスをまとめた(?)本なんだあ。
表紙にそのことが記載してあったら、さらに多くの人が手を伸ばすのになあと思った。
しかも最後の座談会では、伊野尾くんやきゃりーぱみゅぱみゅなど、すごいメンバーが参加しているのだから!
内容は、読みやすいマンガから始まっていて、つかみもばっちり。
今までの学校での常識をもう一度見直していくきっかけとなる。
方法論というよりも、障がい論をまなぶための本といえるのかもしれない。
ここからどう進んでいけばいいのか。続編を期待したい。
 図書館関係者 546150
図書館関係者 546150
具体的な方策というよりも、受け止め方や考え方、視点の転換の指南書だ。
なので、当事者として日々、子どもとがっぷり全身全霊で向かいあっている人が読むよりも、「支援者」として周りにいるにも関わらず、理解がとんちんかんな大人に読んでもらえるといいかもしれない。わかった顔して、多数派の「当たり前」を正義のように振りかざしてくる人に。
誰にもわかってもらえない、と追い詰められた気持ちで、でも逃げ場もなく必死で向かい合っている人に、一番必要なのは一般論ではなく、「聞き役」ではないかと思う。その「聞き役」の心得のひとつとして持っていたい考え方の本かと思った。
 図書館関係者 601014
図書館関係者 601014
まず一言。発達障害の子が困らないのも大事なことですが、
読者が困らないような本にすることも大事なことだと思います。
大事と思う部分を色を変えて強調したいのもわかります。
だけれど、蛍光黄緑という色は万人にとって読みやすい色ではない。
大事で読んでほしいところにその色を使ってしまうこと、
そのことがとてももったいなくて残念なことだと思ってしまいました。
そんな読みはじめだったのでおっかなびっくり読み進めましたが、
内容はとてもまとも。そうだよね、そうできるといいよね、と思いつつページをめくりました。
合理的配慮は正解があるわけではないところが対応の難しいところで、
どこまでなら「無理なく」できると言い切れないところがとても厄介だと思う。
余力があればできることも物理的にも心理的にも余裕がないと、
「無理」に思えてしまうこと、できないこともたくさんあると思う。
子どもの学ぶ環境は保証されてしかるべきではあるけれど、
そのために働く側がどこまでも疲弊してしまっていては担い手がつぶれていくばかりなので、
この本で語られていることが実現できるような環境を整えるのが先決だと思いました。
 図書館関係者 609141
図書館関係者 609141
「学校生活」に特化しているだけあって、教員目線、保護者目線、そしてクラスメイトの受けとめ方など、それぞれの立場に気づかされる。マジョリティの姿に近づけることを良しと考えがちな教員。家にいる時とは違う姿を見せるのは当然だけど、保護者はそれを忘れがち。あの子は困っていたのかと気づくと寛容な子どもたち。気持ちの表し方の選択肢が少ないからこそ、更に困ったことになっちゃうのかな。
 レビュアー 912561
レビュアー 912561
小学校に通う子どもを育てていると、私が小学生だったン十年前と変わっているところももちろんあるのだが、あまりにも変わっていないところも多く、ビックリさせられることも多い。
もちろん、子どもたちがお世話になっていてありがたいと思っているのは大前提だが、子どもたちの親しい友達やクラスメイトが学校に来られなくなったり、長い時間滞在するのが難しくなったりしているのを見聞きすると胸が締め付けられるような気持ちになることもある。
本書は刊行前とのことで、本文からの抜粋は自粛するが、書籍紹介の中にも
「45分間静かに座っていなきゃダメ?」
「協調性ってそんなに大事?」
「学校に行かないと教育は受けられない?」
とあるように、日本の学校で昔から決まっていて、守らなくてはならないルールが、現代や現代の子どもに合っていないのではないかという気持ちになるし、そもそも
「長い時間座っていられない」
「皆と同じ行動を取れない」
なんていう子どもは昔からいたし(何人も見たことあるし)、その頃は認められていた体罰や恫喝を用いて無理矢理言うことを聞かせていたのでは?という気持ちにもなってしまう。
時代は変わって、ゆとり教育などの「教育改革」を経てまた教科や教える量はどんどん増えて、教科書も厚くなったのに、人員は減らされて教員不足、従来通りのクラスサイズで、「インクルーシブ」などのお題目だけは押し付けられ、「あとは現場の先生が頑張ってね」では回っていかないに決まっている。
現場の先生方が身を削って心を削られなくてもよいようなシステムを再構築する必要がある。
このような本が多くの人に読まれて、「ふつう」がアップデートされたらいいと思う。
 教育関係者 454232
教育関係者 454232
教師という仕事をしてハッとさせられることが多々ありました。
「ふつう」とはというので、今まで見て来ている子供達に関して、どの子もみんな色々とあったのでふつうって確かに難しいなと思いました。
そもそも私は日本人の親が1人以上いる、現地語がメインの子供達に週一で日本語を教える仕事をしているので、子供たちそれぞれに事情があります。家では日本人の親とも全く日本語を話さない家庭もあるし、日本人親も小さい頃から現地後で育っているので自分も日本語がほとんどわからないという人もいます。逆に家では徹底して日本人親は子供に日本語で話すという人もいます。
そういう色々な背景の子供が一緒の教室で勉強すれば理解度もですが集中力も全く違います。特に親が日本人でも日本語が話せない場合、なんでお父さんも話せないのに自分が日本語を勉強しないといけないんだ、自分は日本人じゃないし(アイデンティティが)遊びたいのに勉強なんかしたくない。という子にモチベーションを持たせるのって結構大変です。
発達障害とはまた違いますが、こういう事情で子供達に一斉に教えるのが難しく感じたりすることもあるので、この本を読んで色々と勉強になると思いました。
【発達障害の子どもが「困らない」学校生活へ ~多様な特性のまま、日常の「ふつう」を見直そう~】
#安井政樹 #野口晃菜 #NHK出版
発達障害という言葉を教員になって知り、いまではだいたい生徒をみたらどんな特性があるかまでわかるようになりました。
ふつうじゃないと仲間外れにされたり、#いじめ にあったりします。
学校だから集団心理が働くのですが、最近は大多数(マジョリティ)ではなく、少数(マイノリティ)が重要視されています。
このバランスも難しいところではありますが、どちらの視点も大事というのが私の考えです。
紹介します。
#実践事例 や#マンガ で理解しやすく説明されていました。
本は大きく3部構成になっています。
1.日常のふつうを問い直す。
2.個々のバリアを取り除く。
3.#座談会
学校で#ふつう じゃないと見なされる子どもたちの姿。
→多くの子が「ふつう」の枠組みに合わずに苦しんでいる。
#授業中 #行事 #クラス の#ルール など#当たり前 とされていることを改めて見直す。
→45分間静かに座る
→協調性を高める
などの慣習が、ある#特性 の子どもには大きな負荷になるということ。
子どもの思いを大切にする関わり方。
→子どもの「苦手」「つらさ」を聴く、#共感する こと。
#マジョリティ の視点だけでルールや期待が決まっていないかを点検する。
「困った子」は「困っている子」であるという視点。
→行動の裏には#不安 #ストレス #環境要因 など、見えにくい要因がある。
生きづらさの原因として、物理的・環境的・心理的なバリアが学校生活にあふれていることの指摘。
→教室の座席配置、光・音の刺激、時間配分など。
#協調性 と#多様性 の間の溝をどう埋めるか。
→クラスみんなで支えあう雰囲気を作る、ルールの見直し、子どもの特性に応じた配慮をすること。
#無意識のバイアス に気づくこと。
→教員・保護者・友人など周囲の大人・同級生が、知らず知らずのうちに期待や偏見を持ってしまっているケースがある。
#伊野尾慧 さん、#きゃりーぱみゅぱみゅ さんを交えて語る。
普段気づきにくいふつうの枠組みを言語化されていました。





